
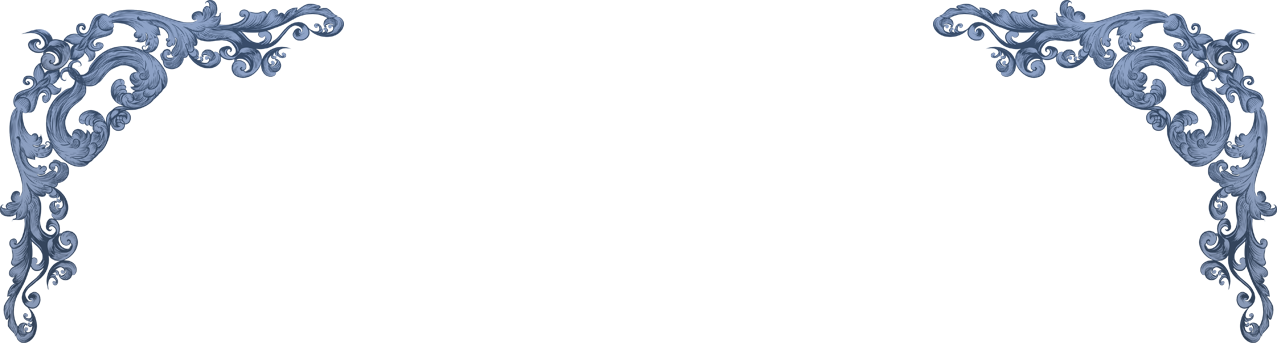

-
突然体が持ち上がり、目線の高さが変わる。
なぜ、体が地面から持ち上がってるのだろう。
- 主人公「え? ええ!?」
- ???「ははっ!」
――愉快そうな、笑い声。
両手でしっかりと私の身体を持ち上げた彼は、
重さなんて感じさせない笑顔を私に向けた。
- ???「袋、落とすなよ。大切なものなんだろ?」
- 主人公「あ、えっと……はいっ」
- ???「はは。いい返事だな。……しっかりつかまって」
-
なぜだか楽しそうに彼は顔をゆるませ、
いっそう強く私を抱える。
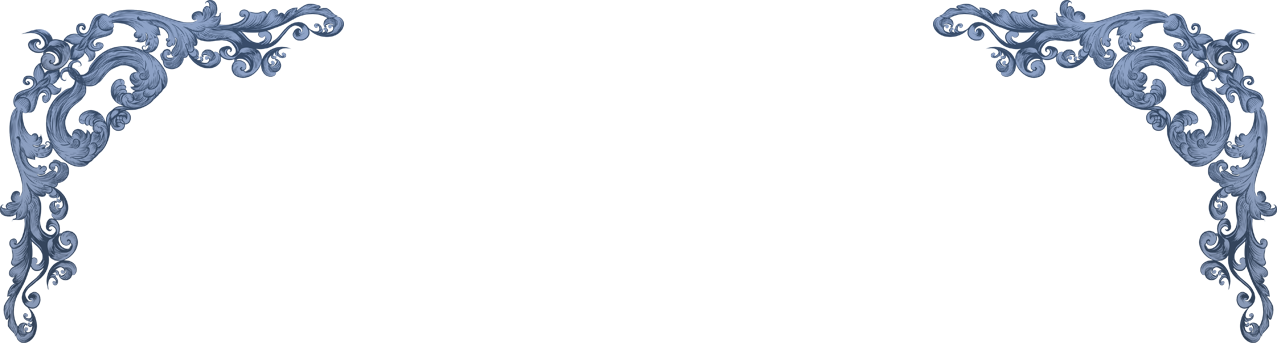

ヴィクトル「鍵を見せてください」-
そう言うのとほとんど同時に、私の手を取る。
そして鍵を確認して納得したようにうなずいた。
- ヴィクトル「なるほど。昨日魔法はかけたんですね。しかし魔法の効力が続かず切れてしまった。君の魔法の力が弱すぎるせいで」
- 主人公「すみま……せん……」
- ヴィクトル「そうならそう言ってくれていい。指示されたことを忘れたり、さらには無視するのと、ちゃんと魔法をかけたのに効力が切れてしまったのでは大違いでしょう」
-
するとヴィクトルさんは懐からハンカチを取り出し、鍵を手に取って何度か磨いた。そして金属部分を爪で弾き、その音を確かめるようにする。
- 主人公「……? なにを……」
- ヴィクトル「もう一度かけてみなさい。ただし今度は、耳に鍵を当てながらです」
- 主人公「耳に……?」
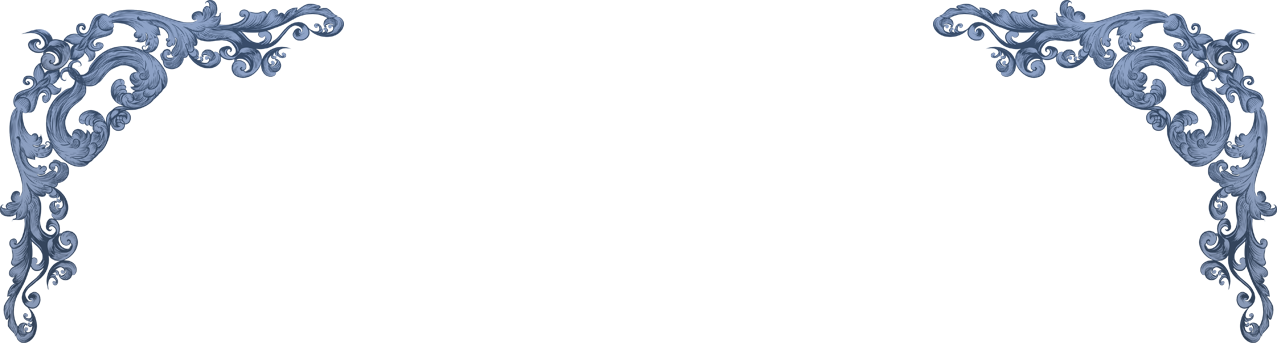

-
彼が手をのばすと、鳥のようなそれは
軽やかに肩に乗った。
すると光の塊がみるみる実体を持ち、
淡い七色の空のような翼を持つ生き物に変わる。
でも、普通の生き物とは違う。
- 主人公「せいれいじゅう、って言うんですか?」
- キャル「知らないのか……」
- 主人公「すみません。普通の動物とは違うんですよね?」
- キャル「……アニマはすべての魔法の原動力。魔法のもと。精霊獣はそのアニマが塊になって意思を持ち一つの生命体になったもの」
- 主人公「へええ、そうなんですか」
- キャル「……普通、知ってる気がするけど……」
- 主人公「は、はい……ごめんなさい……」
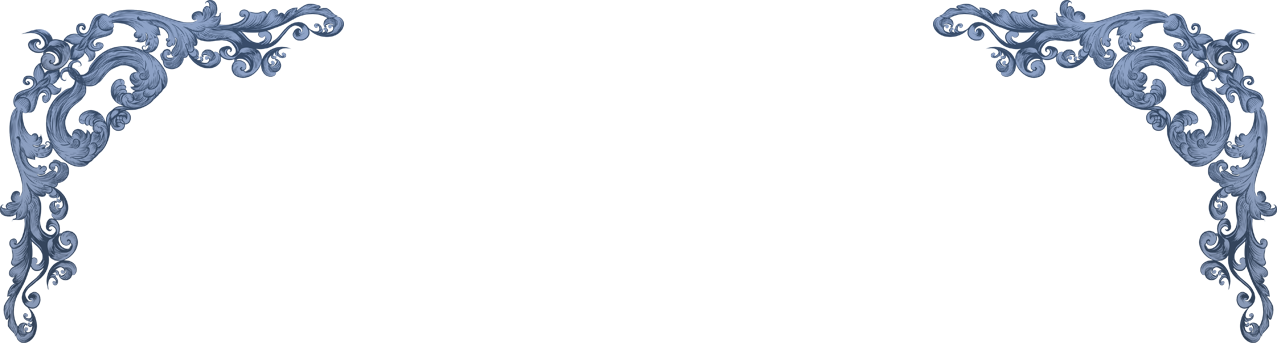

- 主人公「ひゃっ!?」
-
耳元が急にぞわっとして飛び跳ねた。
- 主人公「な、なに……!?」
生ぬるい風にくすぐられたように耳元が熱い。
驚いて硬直していると、横から囁きが聞こえた。
- シルヴァ「ぜんぜん聞こえていなかったみたいですね、僕の話。何を考えてました?」
- 主人公「え……ええっ、とぉ……」
-
困惑しながら横を見ると、
シルヴァ先生はニコニコと微笑んでいる。
- シルヴァ「ああ、でも他の男性のことを考えていたわけではなさそうだ。妙に熱心にこちらを見ていましたし」
- 主人公「それは……まあ……」
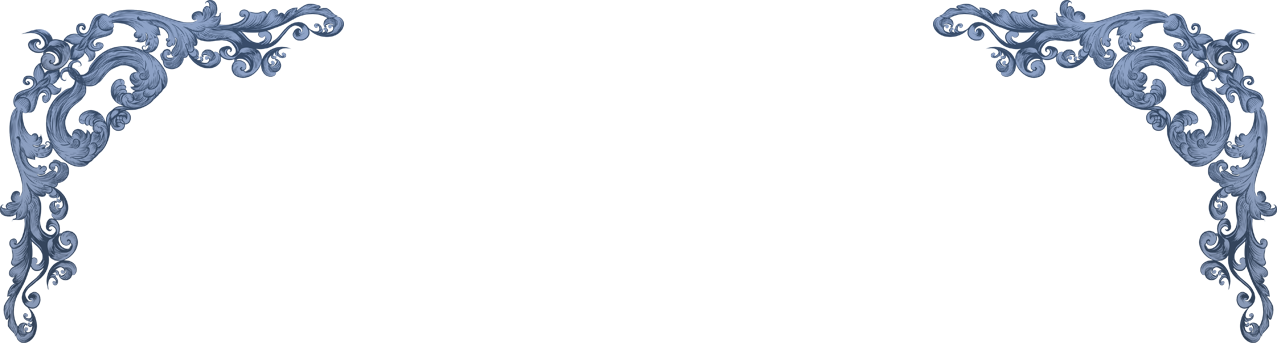

フィン「――ねぇ。君の髪に、キスしていい?」- 主人公「…………い、いいけれど……」
-
ぎこちない返事になってしまった。
彼の声がふわふわと浮ついて、まだ夢の中にいるような心地だ。
- フィン「…………」
-
気配だけは感じて、私はようやく呼吸を再開した。
どうしてそんなことをフィンが言い出したのか、
さっぱりわからないまま。
- フィン「……君はいつも、変わらないね。すべての信頼を俺に預けてくれる……」
- 主人公「……ダメ?」
- フィン「いや……いいよ、そのままで……」
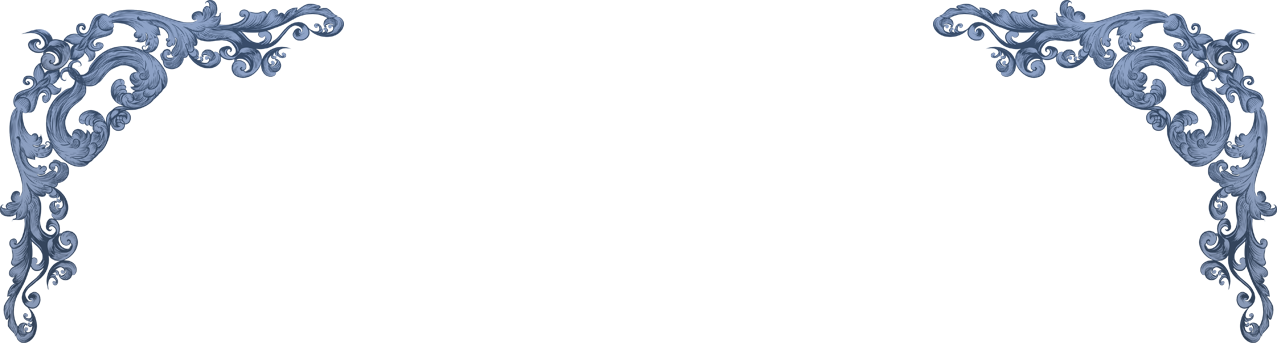

- グラン「そうじゃないんだ!!」
-
今度腕を引かれたのは、私のほうだった。
- 主人公「……っ」
-
グランの腕は一歩たりとも動かぬよう、
私を後ろからきつく抱きすくめた。
大きな背のその人は、私の耳のすぐ近くで囁いた。
- グラン 「そうじゃない。オレは、お前に黙っていたことがあるんだ」
- 主人公「え……?」
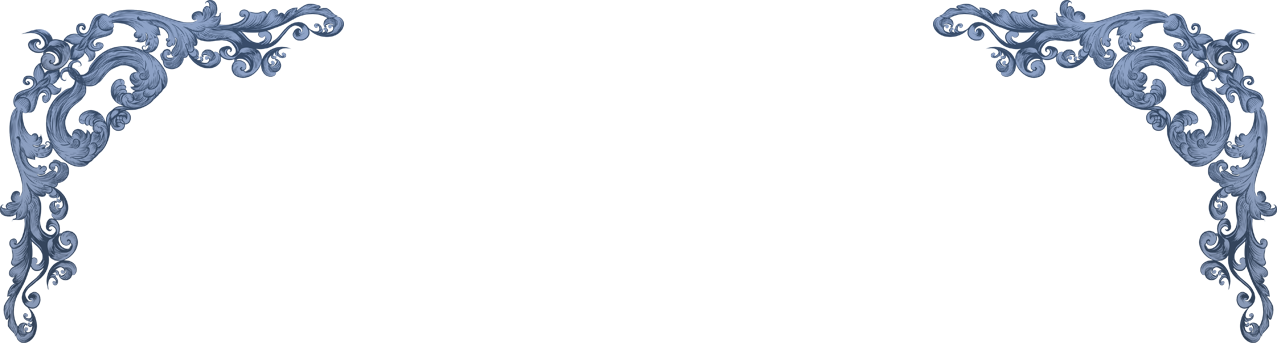

ヴィクトル「ぐっ……」- 主人公「――っ、ヴィクトルさん……!?」
- ヴィクトル「うるさい、騒ぐな……!」
-
そう怒鳴ったヴィクトルさんは、
巨大な鉄板を両腕で支えている。
そうしなければ、
私の上に倒れていたことは明白だ。
- 主人公(私をかばい、守ってくれた――?)
- 主人公「わ、私、今どけます……!」
- ヴィクトル「ダメだ、うかつに動くんじゃない!
こんなもの、すぐに……っ」
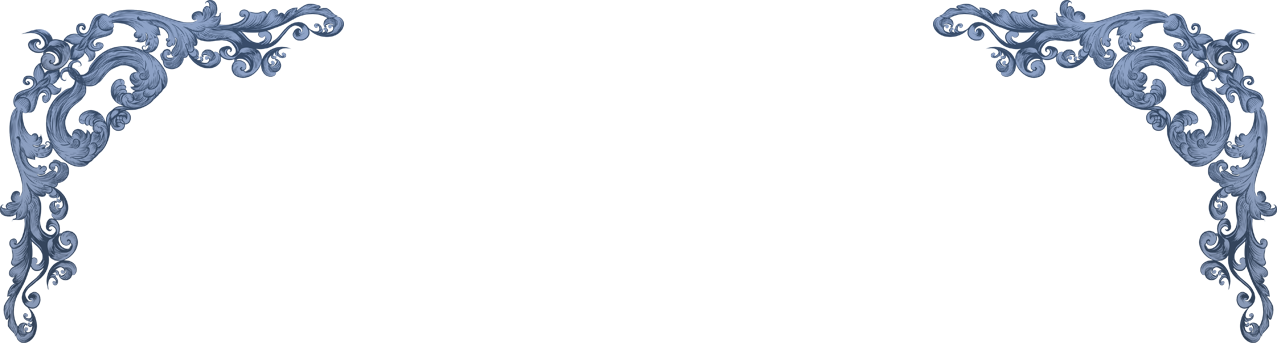

キャル「なんで平気で他人を犠牲にできるんだ。ぼくにはわからない。どうして罪を重ねるのか、わからない」- キャル「早くどこにあるのか言え。言わないならあなたを切り裂いて刻名を奪ってやる」
- 主人公「……っ……」
-
さらにナイフの刃が迫り、歯の根が合わなくなる。
身体が震えて喉が上手く動かない。
吐息が震える。
初めて間近に迫った死の恐怖に、
自分でも顔が引きつっているのが分かった。
- 主人公(どういうこと、なの。
キャルさんが怒っているのはなにに対して?)
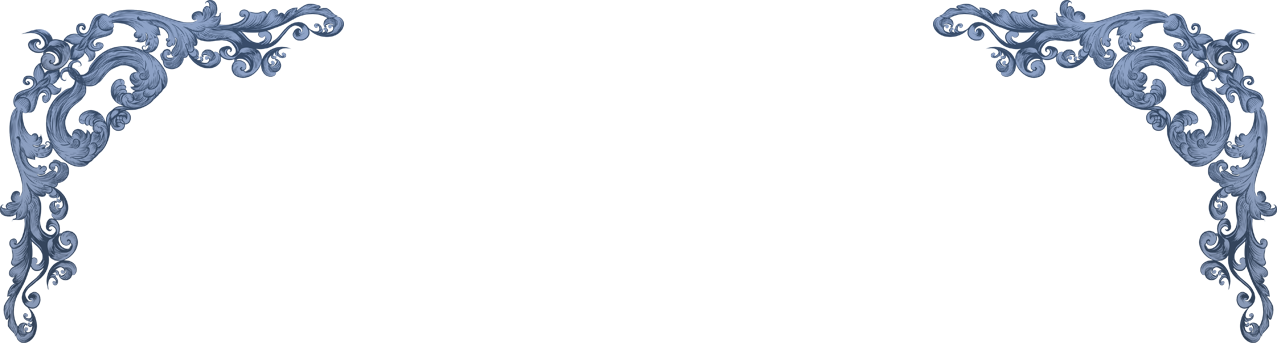

-
抱き寄せると、温かい。
こうやってフィンを抱きしめるのは初めてだった。
私はいつも抱きしめられる側だったから。
- 主人公「私には、フィンはお母さんのことを大切に思っていたように見えたよ」
- フィン「……俺は……」
-
返事がない。
- 主人公「……私は、あなたのそばにいるよ」
- フィン「……また、それか……」
- 主人公「伝わっていないみたいだから。
何度でも言ってあげる」 - フィン「…………」
